「定年後の」、「60歳からの」といったいわゆる【定年本】を僕は、50代のときに何冊か読んだことがある。
確かに書かれていることは、もっともな内容だ。
実践すれば、多くの人が定年後に抱えるお金の不安を解消できるかもしれないし、精神的にも充実した生活を送れるようにも思えた。
でも、実際のところ、自分の役に立ったかというとそうでもない。
なぜ、そう思えたのか理由は2つある。
1つは、定年本の著者の中には、年齢が40代や50代の人もいる点だ。その場合、実際に60歳を過ぎた人を取材するなど外側から見た定年後の実態が書かれている。本人はあくまでも観察者である。つまり、実際に定年になった人間ではない。
僕が知りたかったのは、データではない。データはあくまでも一般論だ。
それよりも定年後の実体験を知りたかった。もちろん、多くの事例の中から自分に類似した内容を知ることはでき、それを自分に当てはまることもできる。けれど、取材された人の話には、多少の誇張や見栄も含んでいるように思え、ありのままの話ではないとつい勘ぐりたくなる。
もう1つは、60歳を過ぎた著者でも、作家、教授、コンサルタント、医者、経営者など社会的地位が高く、おそらく、すでに確たる収入の基盤を持っている人が多い点だ。
定年本の読者は、僕も含め、多くはごくごく平凡なサラリーマンだ。江戸時代なら、貧乏長屋に住む60歳と奉行所で働く60歳くらいの違いがあるだろう。
つまり元々の環境が違う。「いや、あんたからすれば、そうだろう」と思えてしまう部分があるのは、否めない。
したがって、定年本に書かれている内容を鵜呑みにする必要はない。
「そういう考え方もあるよね」程度で十分だ。
いや、むしろ、読まない方が良いのではないかとさえ思う。(僕は読んだが)
例えば、定年後の働き方でいえば、雇用延長、転職、独立、リタイアとさまざまな選択肢がある。なにが正しくて、なにが間違いかなんて答えはない。
だから、あくまでもなにを選択するのかは、本人が決めること、他者と比べるものではないと僕は思う。
僕の場合は、60歳になった当初は再雇用で働くつもりだった。部署も変わり、給与も大幅ダウンだったが、とりあえず収入を得ることができるし、退職し、時間を持て余すくらいなら、仕事をした方がマシだろうくらいに思い、まずは1年やってみようと実際に雇用延長した。
が、結局、嫌になって3ヶ月で辞めた。その後、仕事はしていない。
また、定年後の生活を充実させるためには、「◯◯すべし」、「◯◯してはいけない」といった、いかにもそうしなければ、定年後の生活が無味乾燥になるとでもいいたげなものもよく見かける。
全否定するつもりはないが、余計なお世話かなとも思う。
なにを持って楽しいと感じるかは、人それぞれだろうし、本人が良ければ、いいじゃないか。別に図書館へ行こうと公園のベンチでぼうっとしていても構わないだろう。
結局は、自分が決めることだ。
ただし、周りにとやかくいわれるのは仕方がないだろう。そういうものだ。「確かにそうだよね」と素直に受け入れればいいのでは?
人がどう見ているかなんて、十人いれば十人分の見方があるのが、当然だ。
したがって、自分は周囲からこんなふうに見られているんじゃないかと人の目を気にする必要はない。
人はこう思っているんじゃないかと思っているのは自分なのだから。自分がそう思わなければ良いだけだ。
そうそう最近、あらためて思ったのは、バガボンのパパの、セリフ。
「これでいいのだ!」
これこそ、全てだと思う。まさに名言だ。

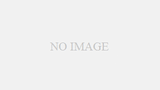
コメント